「選択は全て正解である」
宇宙のことを少しづつ感じられるようになると、この意味を理解し始める。
2025年9月。
自分お誕生月でもあるこの9月に、なぜか「こんな怖そうなの絶対に見ないぞ!」と思っていた「進撃の巨人」を見ることになった。
物語のストーリーはこれから見る可能性のある人もいると思うので、あえて触れないでいこうと思う。
ちょっと怖いかもしれないので、怖いのが無理な人はやめておいた方がいいかもしれない。
いつかみようと思っている人は、ぜひ全てのストーリーを見てから、このブログを思い出してもらえたらと思う。
「進撃の巨人」という物語は、「時間」を円環状の形状にまとめ、プログラムを「経験」に昇華する形をとっているタイプの物語だ。私はアニメはあまり見ないし、映画もそんなに詳しくないし、小説もそんなに読まないので、他にも同じような物語があるのかもしれないが、それにしても、この「円環状の時間」の完成度が凄すぎる。
「時間」というものは、時々YouTubeやインスタで話しているが、実は直線上には並ばない。
本当は始まりと終わりがくっつく「ドーナツ」のような形をしていて、そのいくつかのドーナツが「経験」として存在し、私たちはランダムにそのドーナツの上を量子飛躍のような動きで瞬時に飛び移ることを繰り返し「直線上に並んでいるかのように感じる現実の時間」を体験している。
つまりは、全てはもう存在していて、本当は時間は存在していないし、ただそこにはテーマに沿った「経験」の全ての瞬間が「今ここ」としてあるだけなのだ。
通常私たちがこの「経験」の中にいるときは、全てを直線上に時系列で捉えていくので、「経験が終わる」瞬間に気がつくことは少ない。注意深くなるとわかるのだけど。
わかるようになったとしても、気がつくのは一つのドーナツが完了するのがわかるだけで、「経験」の全体像を見ることができるのは、きっとこの世を去るときだろうと思う。
「進撃の巨人」にはその全てがある。
それが何よりの驚きだった。
私が一番衝撃的だったのは、物語の内容よりも、この構成だった。
私たちはいつも何かしらの「選択」を繰り返しているが、時々「もしもう一つの方を選択していたらどうなったのだろう?」と思うこともある。
「進撃の巨人」の物語の中にも何度も選択が現れ、そしてその「もし」のパラレルワールドもちらっと見えてくるのだが、普通の感覚だと、その選ばなかった世界線を選んだらこうなっていたんじゃないか、ああなっていたんじゃないかと思いを巡らせるが、物語に現れる様々なパラレルのどれを選ぶかという議論ほど、本質を外す議論はないのだということが「進撃の巨人」という「怖いから絶対見たくない」と思っていたアニメによって理解させられるとは思わなかった。
私たちは「A/B」という選択が目の前に現れた瞬間にどちらかを選んでいるのではないんだ。
そうではなく、その瞬間に「A」と「B」というパターンを作り出しているし、それはもうすでに存在しているものであったりするし、ということは本当はどちらの経験もしているのだ。
「今」の自分が例えば「A」の体験しかしていないと思っていたとしても。
そして、その先に行き着くところは実は始りと終わりがくっつくところであるという「点」であって、それは「A」でも「B」でも同じなのだ。
なぜならそれが、「経験」というパッケージだから。
主人公のエレンは常にそのことを言っていて、そしてこの物語はだからこそ私たちに問いかけている。
「今、どうするのか」「今、何を選択するのか」
「正解を探すのは無意味だ」
なぜなら「選択はすべて正解」だから。
それが「宇宙」だし、それが「この世界」だから。
だったら、「好きな方を選べ」
このセリフが、物語全体で一番心に刺さったセリフだった。
やりたいことをやるよ。
そのために今このドーナツの中にいる。
48歳になったこの9月。
「2次元の平面の世界」の「絵」に挑戦する事にした。
それはずっと憧れていたのに諦めていた自分が自分のために持ち込んだ「可能性」だった。
「好きな方を選んだよ」「やっと好きな方を選べたよ」「やっとわかったよ!」
多分ここが、
私の第1章の2000年の歴史の地球が終わり、第2章の幕開けだと思う。
もう何度もブログで紹介したアヴィーチの「ヘブン」という曲が、
主人公エレンにぴったりだと思ったので、また上に貼ってしまった。
主人公の「エレン」は多分私の心の中にもいて、2000年の思いが今癒されているのかもしれません。
この物語を私に届けてくれた全ての存在に心から感謝です。。
「進撃の巨人」は「2000年後の君へ」というタイトルから始まります。
私たち人間のこれまでの2000年のテーマをアニメというパッケージで外側から俯瞰できるように設計されています。
アニメですので、私たちの現実の経験とはデーター量は比べ物にならないくらい少なくなっており、「体験」とは言えないという視点も持てます。
けれど、この内容を「俯瞰できる」ということが、私はものすごく重要な気がするのです。
もうそれができる時代になっていて、そしてこの物語が届けられた背景には、先人たちの体験があったからこそだと思います。
ここから新しい「クリエイト」の時間が始まるのだと思っています。
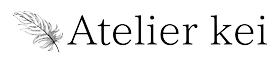

コメント